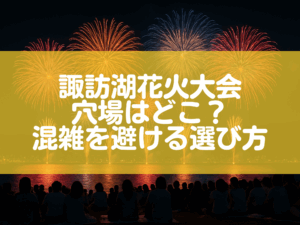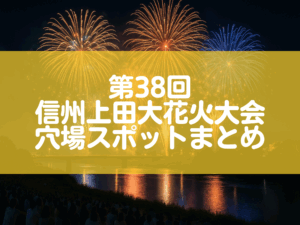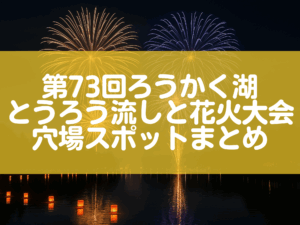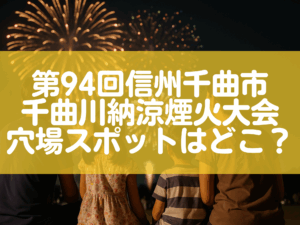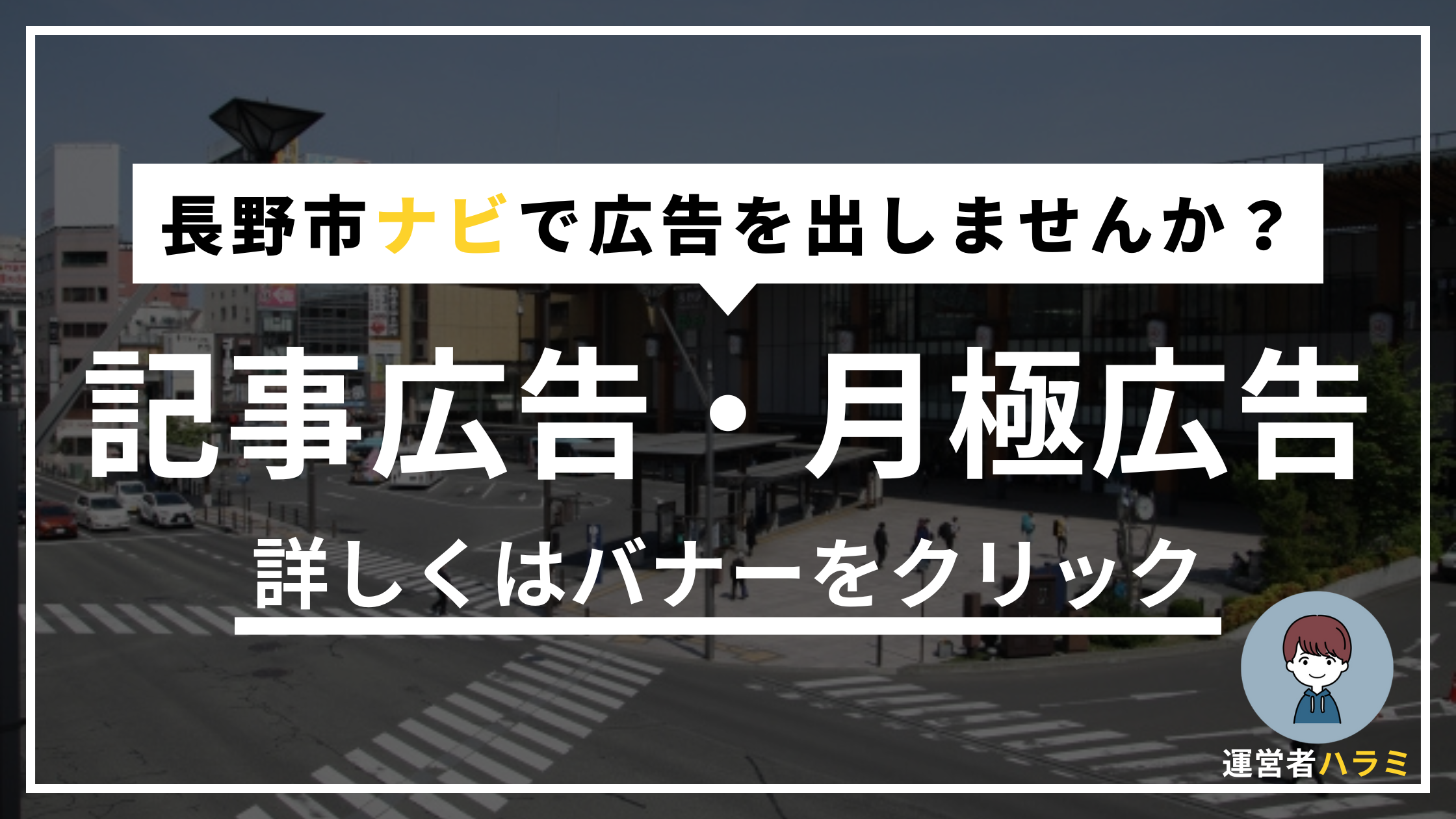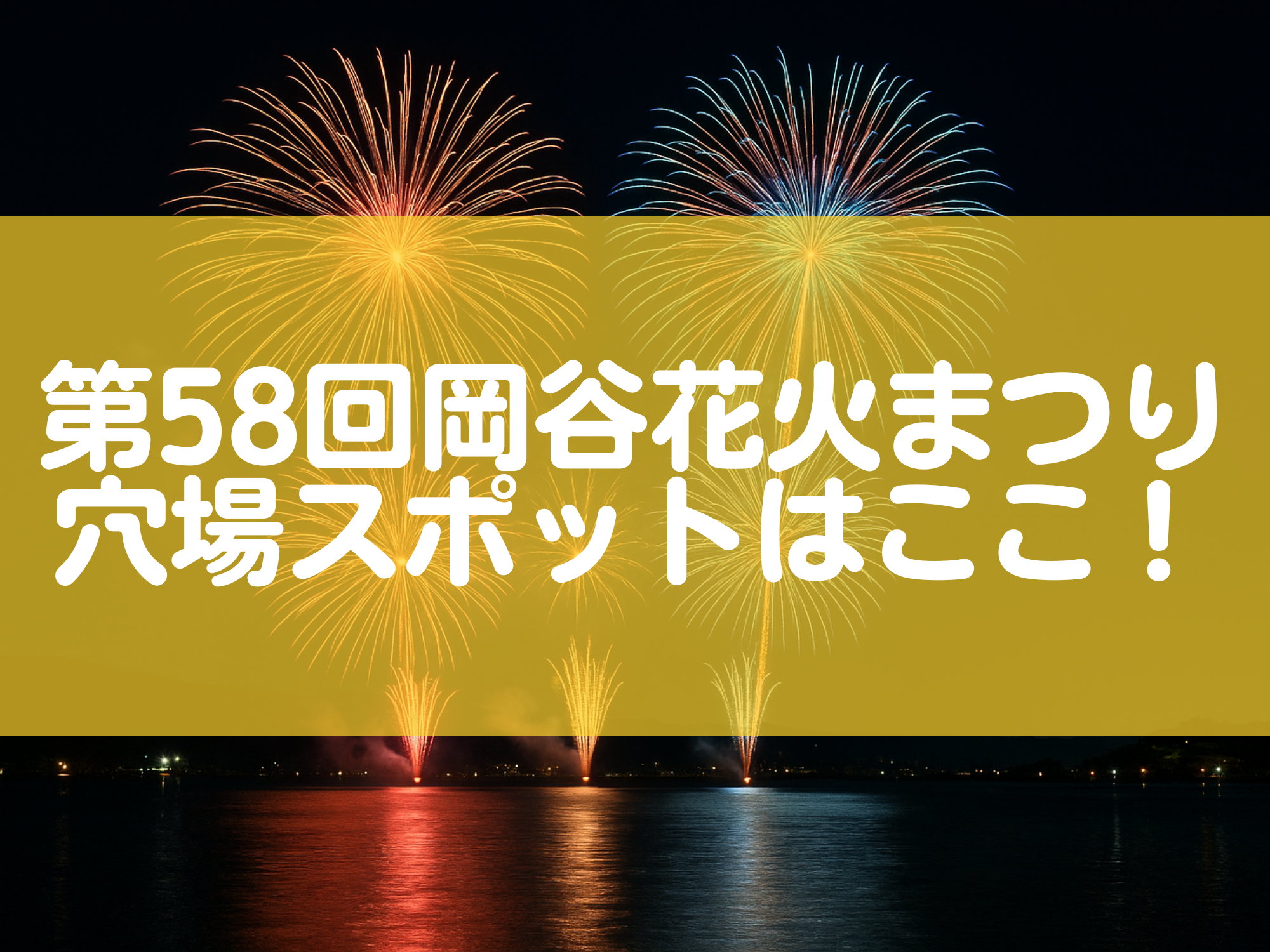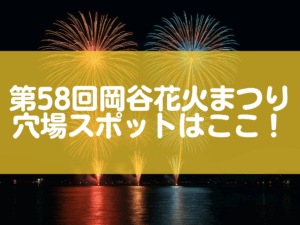花火全体の広がりをとらえるには、高台からの撮影が最適です。その理由は、打ち上げ位置から一定の距離と高さを確保できるため、花火の全景をフレームに収めやすくなるからです。加えて、背景に夜景や湖面が映り込みやすくなり、構図としての完成度が高まります。
ただし、デメリットとしては、打ち上げ地点からの距離が遠くなるため、迫力のある音響や花火の細部が見えにくい点が挙げられます。また、帰路の徒歩移動や夜間の安全対策も必要です。撮影の快適さを優先するなら、昼間の下見や懐中電灯の持参も検討しましょう。
撮影の安定性を確保するには、三脚を設置しやすい地面とスペースの確保が重要です。なぜなら、地面の傾斜や人の往来が激しい場所では、三脚の安定性が損なわれたり、周囲とのトラブルになりかねないからです。
岡谷花火まつりでは、「岡谷湖畔公園」内の広場や「赤砂崎公園」の芝生斜面が一部、三脚設置に適しているとSNSでも紹介されています。一方で、混雑時には三脚禁止となるケースもあるため、事前に公式サイトや案内を確認することが推奨されます。
花火の美しさを際立たせるには、湖面への映り込みを活かした構図が効果的です。これは、夜の水面が自然のミラーとなり、花火の色彩と光が二重に映し出されることで、視覚的に豊かな写真になるからです。
その代表例として、「赤砂崎公園」がよく挙げられます。諏訪湖のほとりに広がるこの公園は、打ち上げ地点からの視界が開けており、比較的静かに撮影に集中できる環境も整っています。特に風のない日には、湖面に鮮やかに反射する花火が印象的なショットを生み出します。
また、「みずべ公園」も比較的打ち上げ場所に近く、角度を調整すれば湖越しの花火構図を狙うことができます。ただし、木や建物によって視界が遮られる箇所もあるため、事前に現地を確認しておくと安心です。