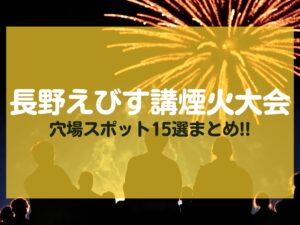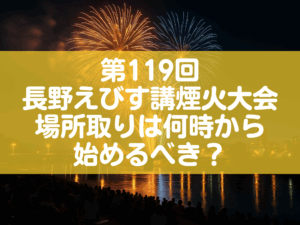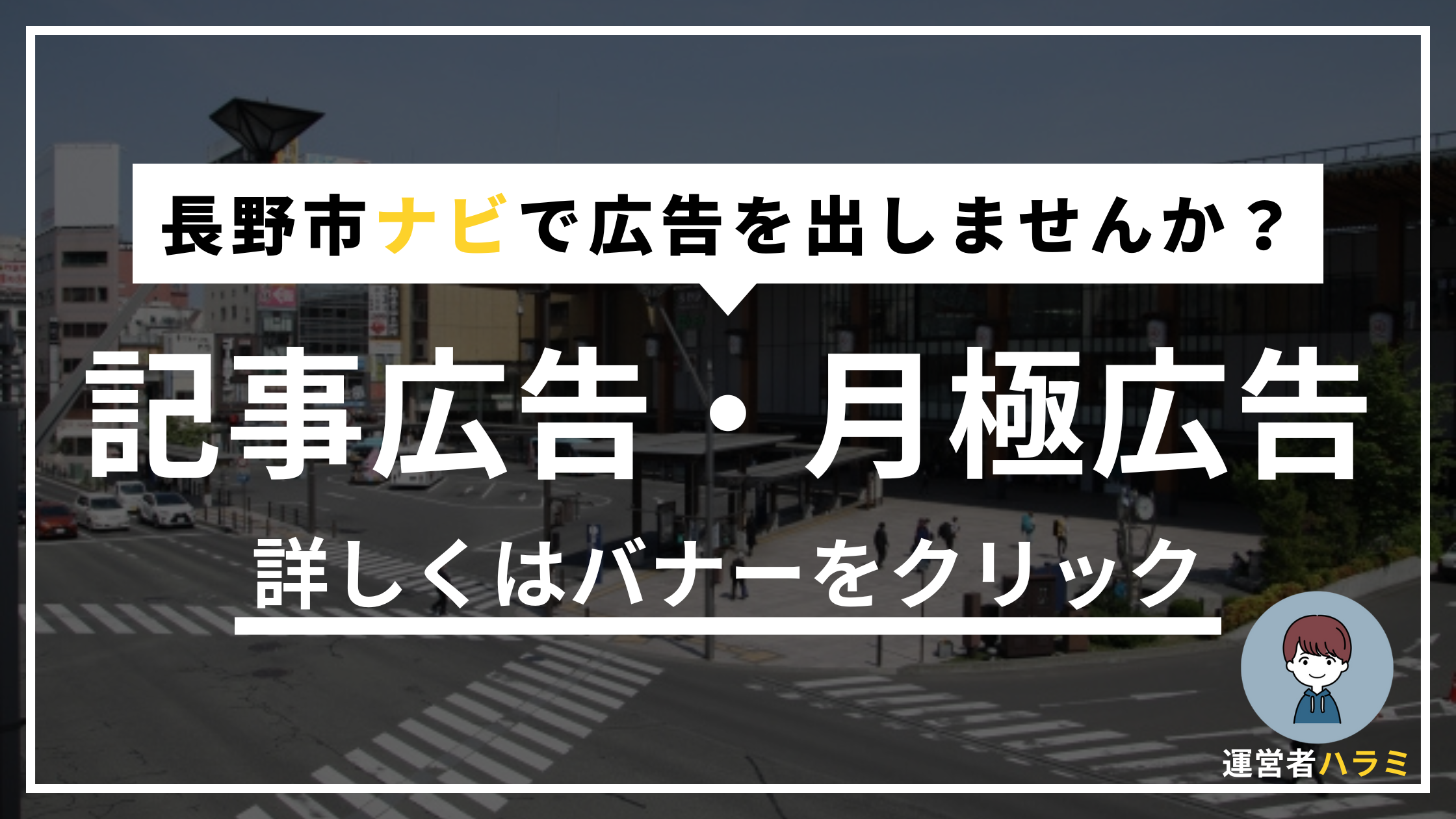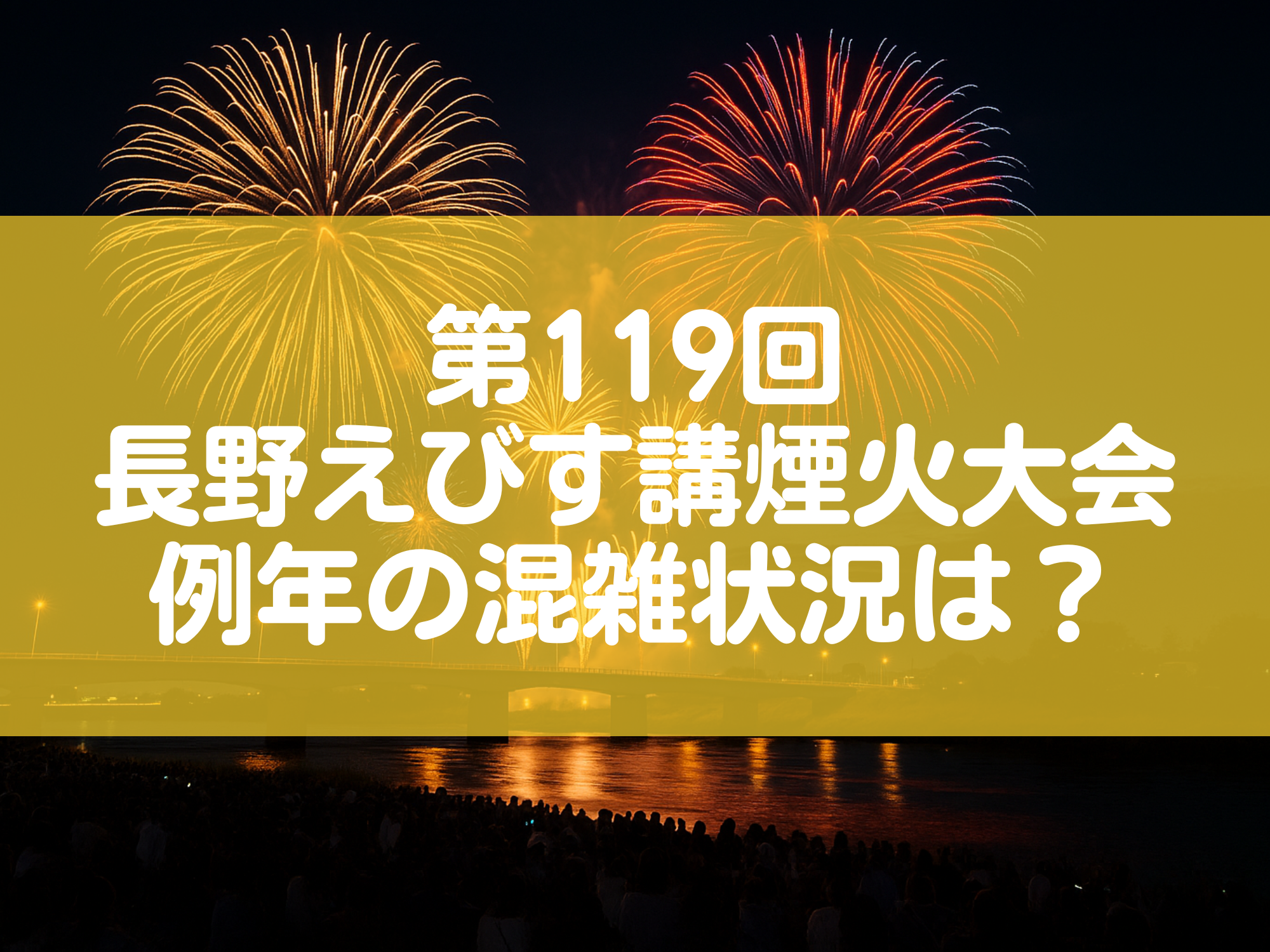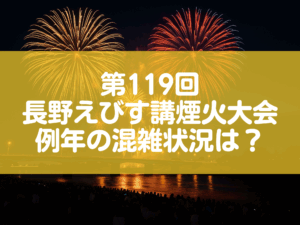第119回長野えびす講煙火大会の混雑はどれくらい?時間帯別に整理
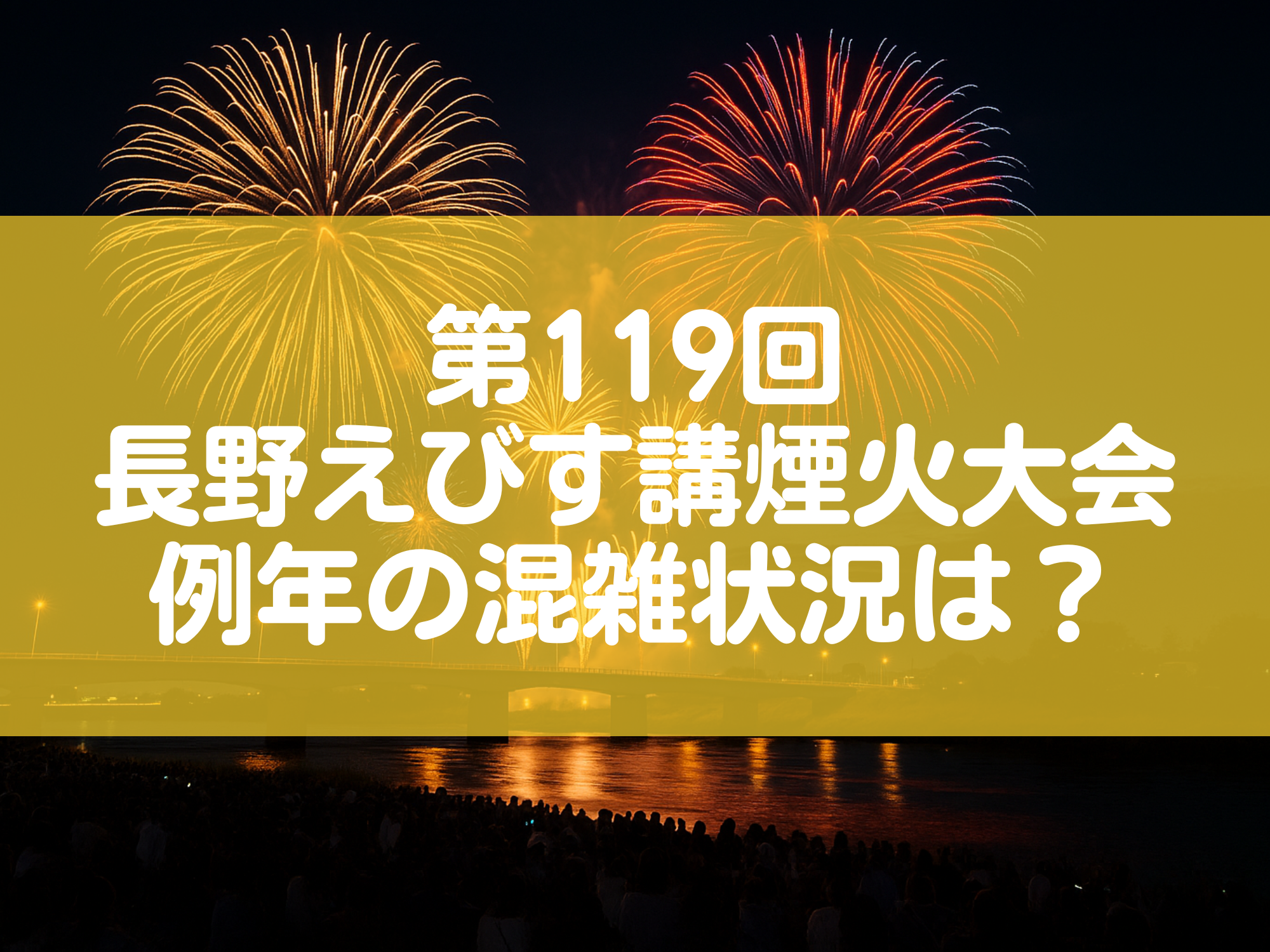
第119回長野えびす講煙火大会は、2025年11月23日(日・祝)に長野市で開催されます。約1万発の花火が打ち上げられる全国的にも有名な花火大会で、例年40万人規模の人出があり大変混雑します。本記事では、混雑をできるだけ避けながら快適に楽しむための情報を「穴場スポット」「アクセス方法」「時間帯別混雑傾向」など多角的に整理し、初めて訪れる方でも安心して行動できるよう網羅的に解説します。
この記事でわかること
- 第119回長野えびす講煙火大会は2025年11月23日(日・祝)に長野市の犀川第2緑地で開催され約1万発の花火が打ち上がる
- 来場者数は例年40万人規模にのぼり会場周辺は昼から夜にかけて大変混雑する
- 混雑回避には昼までの到着や穴場スポット選びが有効で夕方以降は屋台や導線が混雑のピークを迎える
- アクセス方法は電車・車・シャトルバスそれぞれに特徴があり混雑リスクと待ち時間の違いを理解する必要がある
目次
第119回長野えびす講煙火大会の混雑を避けたい人向け「主要情報一覧」
混雑回避に役立つ情報を以下に整理しました。来場前に全体像をつかむことで、当日の行動計画が立てやすくなります。
穴場スポット一覧:見やすさ◎
| スポット名 | 特徴 | 混雑度 |
|---|
| 長野大橋 | 打ち上げ地点に近く迫力満点 | やや混雑 |
| 丹波島橋 | 横から観覧、比較的空いている | 少なめ |
| 日赤病院周辺 | 全体を広く見渡せる視野 | 中程度 |
| 南長野運動公園 | 家族向けの広いスペース | 少なめ |
あわせて読みたい
知る人ぞ知る!長野えびす講煙火大会2025の花火がよく見える穴場スポット15選!
2025年11月23日(日・祝)に長野市で第119回長野えびす講煙火大会が開催されます! 例年通りにいけば、約40万人もの人が長野えびす講煙火大会の花火を観に来るので、会…
あわせて読みたい
第119回長野えびす講煙火大会の場所取りは何時から始めるべき?混雑の傾向と対策
長野の晩秋を彩る「第119回長野えびす講煙火大会」。例年多くの観覧客で賑わい、場所取りに悩む声も少なくありません。本記事では、有料席・無料席・穴場スポットを整理…
アクセス手段別混雑度一覧:車・電車・徒歩◎
| 交通手段 | 特徴 | 混雑度 |
|---|
| 車 | 臨時駐車場なし。駅周辺駐車場は早い時間に満車 | 高 |
| 電車+徒歩 | 長野駅から徒歩30分、安茂里駅から徒歩15分 | 中 |
| シャトルバス | 主要拠点から運行。花火後は待ち時間発生 | 高 |

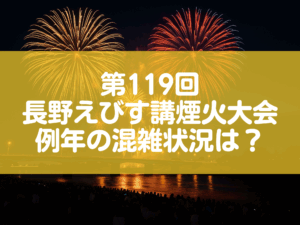
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!