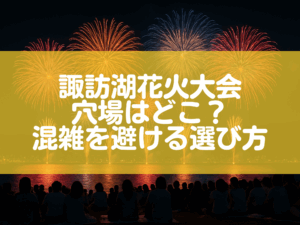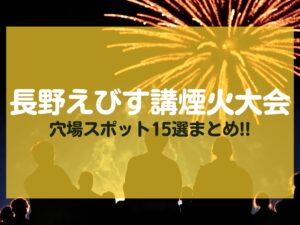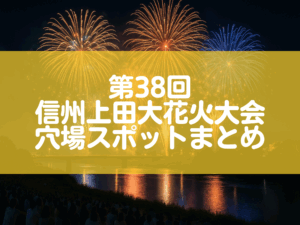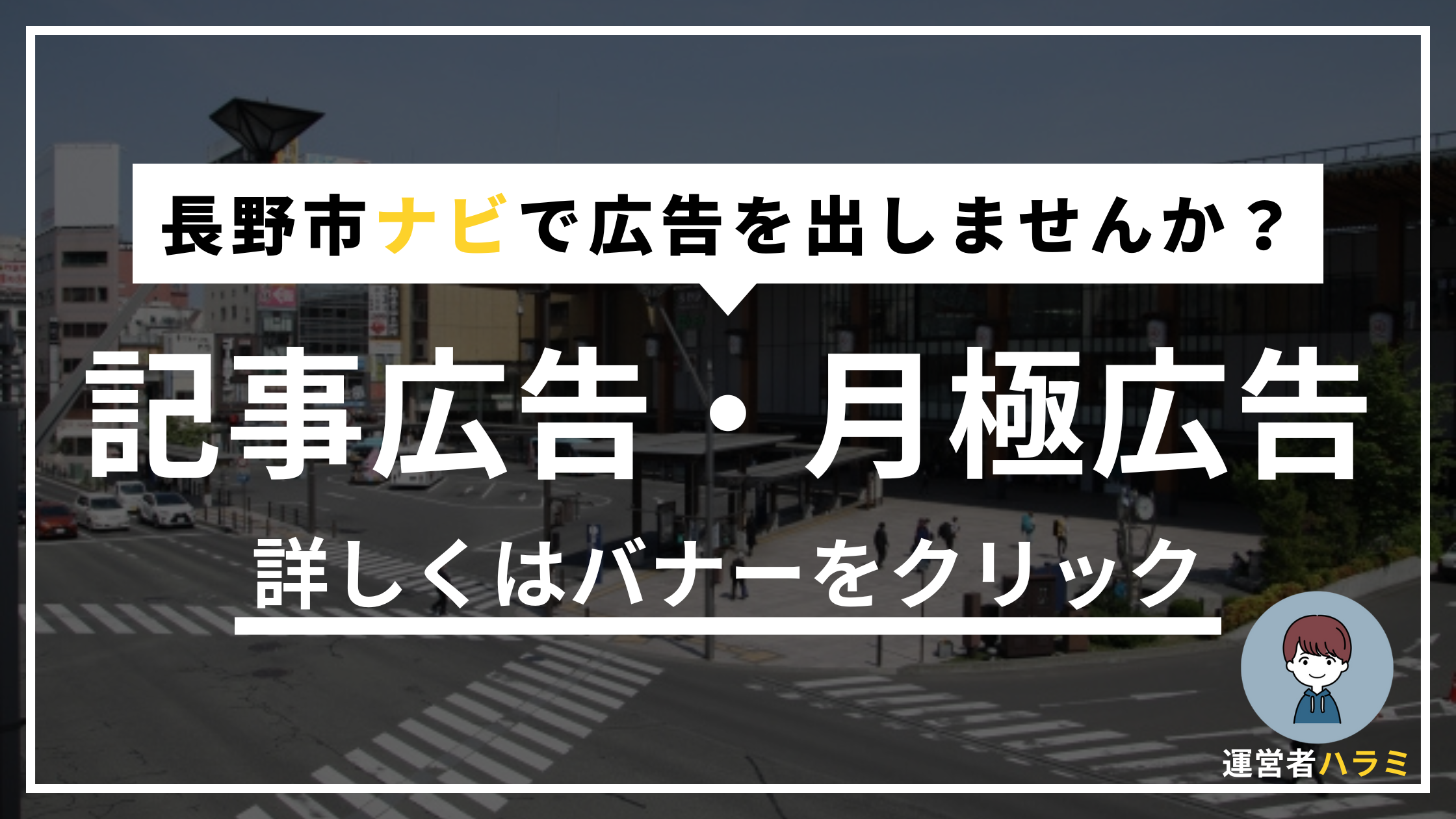第18回安曇野花火の会場である御宝田遊水池へは、JR明科駅から徒歩でアクセスすることが可能です。徒歩ルートはおおよそ20分程度と案内されており、駅からは川沿いに整備された道を進むことで比較的スムーズに到着できます。駅を出た後は、案内板や係員の誘導がある場合もあるため、混雑時でも迷う心配は少ないとされています。
このルートの利点は、電車でのアクセス後すぐに徒歩移動ができることと、会場に向かう人の流れに乗れば道に迷いにくい点です。特に公共交通機関を利用したい方や、シャトルバスの待ち時間を避けたい方には適しています。
一方で、デメリットとしては、暗くなってからの徒歩移動にやや注意が必要な点が挙げられます。川沿いの道は場所によって照明が少ない箇所もあるため、懐中電灯やスマートフォンのライトを活用すると安心です。